ブルーベリーの病害虫問題
おばんです。
4日連続で書いています。
奇跡です。
明日は、修理に出しているロードバイクを受け取りにでも行きましょうかね。
6年ぶりのロードバイク!!
やや興奮しています。
そんなこんなで、今日はブルーベリーの病害虫のお話です。
先日、こんな記事を書きました。

その中で、ブルーベリーは 無農薬で栽培できる と書いてあります。
確かに、定期的な薬剤散布をしなくても、栽培に成功しているケースも多いですし、庭に植え付けたとしても、発生はほとんどしないでしょう。
ほかの果実に比べると、虫もつきにくく、耐病性もあるのは事実ですが、やはり植物である以上、虫はつきますし病気にもなります。
だから「私は絶対無農薬で栽培するのだ」という方は結構なのですが、対処法を知っていないでそのようなことを言っているのであれば、ただの怠慢 でしかないとぼくは思います。
となると大事なことは、敵を知り、対策を講じる 知識です。
これに尽きます。
そこで今回は、ブルーベリーを栽培するのに気をつけるべき病害虫対策についてまとめました。
これから庭に植えてみたいなぁとお考えの方も、ここでの知識を抑えておくだけで、ブルーベリー博士へ近づけます。
ではさっそく、ブルーベリーの病気、害虫に分けて確認していきましょう。
ブルーベリーの病気
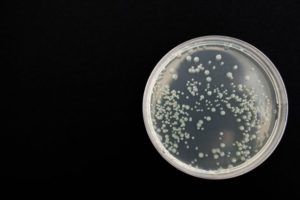
まずは、病害虫の 病気 の方について説明します。
灰色カビ病
開花期に、花房が褐色に変色して、表面に灰色のカビが発生する病気です。
発生条件は、低温、多湿 で発生しやすく、おもに標高の高い高冷地や寒い地域に多い傾向です。
また、肥料が過多、間隔が不十分な密植状態(風通しが悪い)でも発症しやすくなります。
放っておくと、植物体や腐敗した葉、残渣から繁殖を続け、伝染源となり広範囲に広がります。
発生しやすい時期は、4月~11月
とくに、春先の気温が低く、梅雨の時期には注意が必要です。
秋から冬にかけても、発症が増える傾向があるので注意しましょう。
ぼくも、暖地とはいえ、露地の育苗をするのに、過湿・密植状態になりやすいので、気をつけないといけません。
・早めに変色した花を摘み取る
・剪定をして、なかったことにする
・落ち葉を拾って清潔にする
・農薬散布(トップジンM、オーソサイド、カリグリーンなど)
枝枯れ病・枝腐れ病
文字通り、枝が枯れたり腐ったりする病気であり、密植している際に、発生しやすい傾向があるので、風通しが良い管理を心がけましょう。
また、土壌の過湿状態、窒素が多い と発症しやすいです。
・剪定をしてなかったことにする
・水やりをストップして、過湿状態から脱却させる
・通気を良くする
根腐れ病
梅雨が明けた夏ごろ、葉が黄色くなり、新芽が伸びなかったり、根が腐って株全体が枯死する病気です。
ラビットアイ系は、土壌の適応力があるので、あまり発症はしませんが、土耕栽培のハイブッシュ系ではよくみられる傾向があります。
粘土質で水はけの悪い土壌、過湿状態 で多く発生します。
土耕で植え付ける際は、なるべく大きな穴を掘り、土壌改良をすることで防ぎましょう。
とはいえ、鋸南町のような温暖であり、粘土質な土地では、ハイブッシュ系は絶対手を出してはいけません。
知り合いのブルーベリー農家さんに話を聞くと、全員口をそろえて「千葉でハイブッシュ系は植えるな」とおっしゃります。
なぜって??
5年後あたりに枯れるから です。
5年後あたりというのが、いやらしいですよね。
やはり土壌が合わないのでしょうか。
なのでぼくは、養液栽培でハイブッシュ系を育てるつもりです。
暖地の土耕栽培でやりたいという方は、潔くラビットアイ系一択 でいきましょう。
【脱線小話】
現在、ど根性栽培をしている圃場が、大雨になると床下浸水かというくらい水浸しになるんです。
粘土質の水はけの悪い土壌。
夏はカピカピになります。
そんな悪条件の土地に80本近く植えて、根腐れを起こしたのは、5株程度。
これを多いとみるか少ないとみるかは人それぞれですが、個人的な感想として、「よくここまで育ったな」という感じです。
ラビットアイ系だから大丈夫!!かと思うのですが、あまりに条件が悪いので、一度掘り起こして、土壌改良及び排水処理を考える予定です。
5年経って、もっと根腐れ病の苗が出てきたら嫌なので(笑)
ちなみに、植え付けから2年近く経ちますが、生育は良好です。
水はけさえよければ、粘土質の土壌でも栽培可能です。
土地をお持ちの方は、試してみる価値ありです。
【小話 完】
だいぶ話がそれましたが、
・土壌改良をする
・水やりをストップして、過湿状態から脱却させる
他にも、サビ病などもありますが、とりあえず下記のことを抑えておけば大丈夫です。
・常に風通しをよくする
・春先(特に梅雨時期)、秋口の過湿に気をつける
・水はけが悪い土地は、土壌改良をする
大事なのは、早期発見早期治療です。
ブルーベリーの害虫

続いて、病害虫の 害虫 の方を説明していきます。
コガネムシ
成虫は若木の柔らかい新芽を食べ、幼虫は根を食べるどうしようもないくそったれです。
コガネムシの厄介なのは、やはり幼虫の方ですね。
なぜって、地中の中にいるわけですよ。
だから、植物が「おやおや君、元気ないね」という状態ならないと分からないんです。
なんなら分かったとしても、掘るのが億劫で、放置しちゃったりするので、厄介。
(元気のない株が4つあるけど、絶賛放置中です。)
対処法としては、元気のない株を見つけ次第、スコップで掘り起こして確認、もしくは農薬散布するって感じでしょうか。
成虫は、収穫期前後の7月下旬~8月上旬にかけて発生します。
ただし、大量発生しない限りは、心配することはありません。
とはいえ、圃場の定期巡回はしっかりとおこない、見つけ次第 捕殺 する習慣をつくっておくのがベターでしょう。
・圃場の定期巡回+捕殺
・元気のない株を掘り上げて、根に幼虫がいない確認+捕殺
・農薬散布(ダイアジノン、オルトランなど)
カミキリムシ
カミキリムシも厄介ですね。
鋸南町には、2万本近い桜が植えられているのですが、こいつらのせいで何百本という木が枯れています。
カミキリムシは、株元などに産卵して幼虫が食入りし、株を枯らしてしまいます。
夏場に被害が見られ、株元におがくずのような跡があれば、幼虫が中に入って間もない段階なので、針金か何か細いもので食入口から刺し殺します。
・圃場の定期巡回+刺し殺す
・農薬散布(モスピラン液剤、ダントツ水溶液など)
アブラムシ類
春先から初夏にかけて、柔らかい新芽を吸汁します。
ぼくは成虫と吸われた葉、もろともむしり取りなかったことにしています(笑)
・圃場の定期巡回+捕殺
・農薬散布(モスピラン液剤、ダントツ水溶液など)
ケムシ(イラガ等)
開花期ごろに発生が見られ、つぼみや花、葉などが食害されます。
よく葉の裏にいるので、圃場巡回の際に食痕があれば、葉をめくって確認してください。
見つけ次第、即 捕殺 です。
イラガは刺されると痛いので、捕殺する際は、必ず手袋+いらない紙とかで行いましょう。
また、8月頃になると、ミノムシが葉にぶら下がっていたりする光景もたまに見ます。
これを放っておくと、翌年虫が大量発生してしまうので、1匹ずつ容器に捕獲して、そのまま燃やしてしまいましょう。
・圃場の定期巡回+捕殺
・ミノムシは燃やす
・農薬散布(オルトラン、グレーシアなど)
まとめ

いかがだったでしょうか。
いろいろと説明しましたが、大事なのは 早期発見早期治療 と 発生しにくい環境作り です。
通気を良くして、株元などの除草を定期的におこなうように心がけましょう。
また、樹を定期的に観察して(特に葉の裏)、害虫がいたら捕殺するなど、被害を最小限に抑えられるよう日頃から目視で確認することが大事です。
気づいた時には、恐ろしいくらい発生しているなんてこともあり得ない話ではありません。
どうしても手に負えない場合には、薬剤に頼ることも必要です。
無農薬栽培にこだわるのは結構ですが、まずは適正な管理に目を向けてブルーベリーと向き合っていきましょう。
ではまた!
